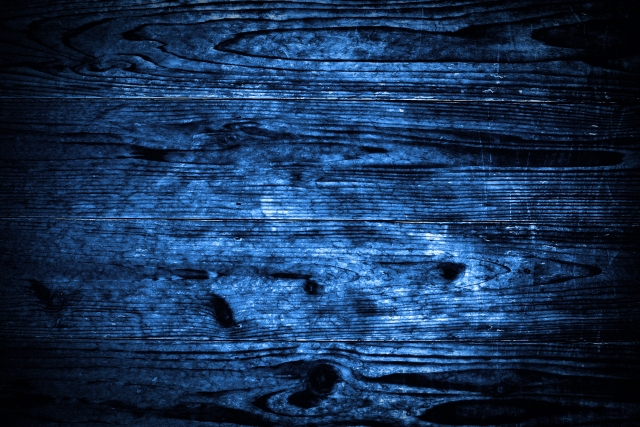ゆーきの奴にプレゼントを買うのに、思いがけない道を通ることになったもんだ。この複雑な気分を紛らわせるには……そうだ、あそこへ行こう。
俺の足は、いつもの喫茶店へと向かっていた。
「いらっしゃい……やあ、友部君じゃないか。久しぶりだね」
「こんちは、マスター」
そういえば、このヒゲのマスターの店に来るのも、しばらくぶりのような気がする。……相変わらず、いつ来ても繁盛してるぜ。
「あれ? 友部君……ゆーきちゃんは?」
「家で留守番してます」
「ふうん……。で、何にする?」
「そうですねえ……炭火、お願いします」
今の気分と、この店のメニューを照らし合わせ、一番濃厚な香りのする物を頼む。頭のもやを消す時の、定番メニューになりつつあるな、これ。
「炭火コーヒーね。かしこまりました」
マスターの復唱を聞きながら、タバコを取り出して、火を付ける。ちりちりちり……と燃える炎をしばらく見つめていると、カウンターの向こうから声がした。
「友部君、また悩んでるね?」
「えっ……? なんでわかるんです?」
「ゆーきちゃんと暮らし始めてから、君が一人で来るときってのは、何か悩んでるときだろう? しかも、頼むのは大抵炭火。何か、紛らわしたい、って思えるんだけどな」
「……………………」
「おっと、気に障ったらごめんよ。どうしても、気になってね」
「そんな、気にして貰うほどの……」
「はははっ……君もそうだけど、ゆーきちゃんの方がね」
「あらら……」
「どうして君が悩んでるのかは訊かないよ。でも、何度も言ってるように、ゆーきちゃんは、泣かせないでくれよ」
「やだなあ、『泣かせないでくれよ』って、別にあいつは、マスターの娘じゃないでしょ?」
「ふふふっ……まあね。でも、気になるんだよ。あの娘、すごく良い娘だからさ」
「ですね……」
「はい。炭火コーヒー、お待たせ」
「あ、どうも……」
砂糖とミルクを入れてかき混ぜながら、香りを嗅ぎ、店内の喧噪に耳を傾け、一口すする。
「久々で、うまいなぁ……」
「ありがとう。友部君に誉められると、安心するな。だいぶん前からの常連さんだしね」
「おだてないで下さいよ。……でも、そうか……大学入学当初から通ってるから……今、俺が二十五で……えっ? 七年?!」
「うん。そうなるね。長いだろ?」
「確かに……」
「そういえば、ゆーきちゃんを連れてきたのは……去年の、春だったよね? もう一年以上経っちゃったんだねえ……」
「マスター、よく覚えてますね」
「えっ? まさか友部君、忘れてたとか?」
「……ええ。実はそうなんですよ。ずっと一緒にいて、なんだか、最初っからうちにいるような気がして……つい……」
「あらら……」
それから俺は、今日のいきさつを話した。岩城の件は、いくぶんぼかして、だが。
「なるほど。いい話じゃないか。きっと、ゆーきちゃんも喜ぶと思うな」
「ええ。あいつの喜ぶ顔が、何よりですよ」
「まったく。でも、友部君……」
「はい?」
「私に言わなかった悩みの原因は、今は、あの娘に言わない方がいいね。きっと」
「…………………………ですね」
それからは、何を話すでもなく、時間が過ぎた。
忙しく注文を取って回るウェイトレスさん達、復唱しながら、次々にコーヒーを入れ、料理を作っていくマスター、他の客の喧噪、タバコの煙、コーヒーの香り……
「あ……と……」
俺は、口に運んだコーヒーカップの中が、空であることに気付いた。タバコも、随分進んでいる。
「そろそろ、帰ります」
「ああ。いつもありがとう。ゆーきちゃんによろしくね」
「分かりました。それじゃ……」
店を出て、今度こそ家に向かおう……と足を踏み出す。……その時、何だか、店の中から誰かが俺を見ているような気がした。
だが、振り向いたところで分かるはずもない。そこにはただ、『Cafe Angel』という、この店の看板があるだけだった。
「気のせい、だよな」
確認も込めてつぶやき、俺は歩き出した。
「ん?」
家に着き、鍵を開けようと思っていたところ、内側からドアが開いた。
「わっ?!」
家から出てきたゆーきが、眼前に立ちふさがる人影―つまり俺だが―を見て、のけぞり気味に驚く。
「あっ……潤一さん! おかえりなさい! 早かったね!」
俺と分かるや、思い切り顔をほころばせるゆーき。なんか、今日はいつも以上にホッとするな。俺は、ゆーきをその場で思い切り抱きしめたい衝動をぐっと抑え、笑顔で返した。
「何だ? 今から買い物か?」
「うん! そうだ、潤一さん、何か食べたいもの、ある?」
「うーん……いや、お前に任せるぜ、ゆーき」
「はーい! じゃあ、いってきまーす!」
「ああ。気をつけてな」
スキップにも見えるほどの、軽やかなゆーきの足取り。その背中が見えなくなってから、俺は家に入った。
「………………」
しん、と静まり返った部屋の中。香水とかでは決してない、あいつの匂いが、まだ残っている。
「一年、か……」
この部屋で起きた、色々なことが頭をよぎる。
二人で笑い、二人で泣き、二人で怒り、そして、二人で愛し……
自分で言うのも何だが、満たされていると思う。ずっと、続かせていこう、そう思う。
まあ、それはさておき、ゆーきがいないのが、今は好都合だ。俺は、岩城に渡す写真を探しに掛かった。
「よし、これが一番かな……」
アルバムを引っぱり出し、検討することしばらく。よさそうな一枚が見つかった。いつだったか、遊園地に行ったときの物だ。二人並んで、全身が写ってる。俺はそれを、定期入れにしまい、捜し物の後始末をした。
「はあ……」
一段落すると、何だか、虚脱感が襲ってきた。ゴロリと身体を投げ出すと、自然にまぶたが重くなり、天井が降りてくるような感覚と共に、俺は眠りに入った……。
・
・
・
夢を見ていたようだ。でも、その夢の登場人物は、もういない。俺のいるのは、真っ暗な、粘ついた沼。ふとしたことで口を開け、俺をのみこみ、なぶり、さいなむ、記憶の沼……。あたりを飛び交う、断片的なイメージ。増幅された印象。怒り。嘲笑。涙。後悔。自虐。叫び。快楽さえ、苦痛。苦しい……誰か……!
「………………さん……じゅんいちさん…………!」
声が聞こえる。……誰?
「潤一さん……! しっかり……ねえ…………」
柔らかい手、頬を打つ手、ぴたぴた、ぴたぴた……。
「潤一さん……! 潤一さんってばぁ……!」
感覚が、はっきりしてきた。まぶたから、光が飛び込んでくる。
「ゆ……ー……き…………?」
「そうだよ、潤一さん! 分かる?」
「ああ……なんか、うなされてたみたいだな……」
体を起こす。……眠ったにしては、ずいぶんと重く感じる。
「うん……。こんなに冷や汗かいてるよ……」
顔中を拭っていく、ゆーきの乾いたハンカチ。
「………………」
目元のあたりを拭うとき、手が一瞬止まり、本当に心配そうな目が、俺を見つめた。
「もういいよ。ゆーき。ありがとう……」
はあ、とため息をつき、俺はようやく現実世界に戻ってこられた。
「潤一さん、ご飯、食べられる?」
「……そうだな。腹は減ってきてる。いただくよ」
「はーい、じゃあ、今から作るね」
いつもの調子に戻そうとする俺に、ゆーきも、同じように答えてくれた。
壁にもたれ、ぼんやりとタバコをふかす。とりあえず、あの夢を身体から追い出そう。そう思いながら、俺はしばらく、タバコの酩酊に浸ることにした。
「おまたせー! ご飯できたよー」
「おっ……今日は凝ってるじゃないか」
「へへぇ、いいでしょ?」
今日のメニューは、野菜炒めの中華風あんかけと、ご飯、そして、溶き卵入りスープ。いろいろやってくれるぜ。
「うん、うまい!」
「よかった!」
飯を喰っている間は、余計なことを何も考えないで済む。まあ、それだけコイツの作る飯がうまいってことだ。
「よし、ごちそうさん!」
「はい、おそまつさま!」
ゆーきの差し出してくれた冷たい麦茶を飲んで、食事を締める。
ここから先は、なんとはないダラダラした時間が、寝るまで続く。
「(今日は……そうだな……)」
俺は、ひとつ音楽をかけることにした。
「あ……」
洗い物を終えようとしていたゆーきも、その曲に振り向く。スピーカーから流れるのは、ゆったりとした流れの、ピアノ曲。久しぶりにかける曲だ。
「ゆーき、コーヒー、いれてくれないか?」
「うん」
ゆーきのいれてくれたコーヒーを飲みながら、黙って、澄んだピアノの音色に耳を傾ける。……今度、何かコンサートに連れていってやるのもいいかもな。そんなことを思いつつ、俺は、この系統で、別の曲を流していった。
そして、気がつけばもう結構な時間が過ぎた。
「そろそろ寝るか……」
「そうだね……」
布団を出そうとしていたとき……
(ピリリリリッ…… ピリリリリッ……)
部屋の隅に置いている、携帯電話が鳴った。
「ひゃっ?!」
音楽の余韻にうっとりとしていたゆーきが、驚いて声を上げる。
俺は、ゆーきに目で詫びながら、電話を取った。
「もしもし」
『あ……友部君……? 私……』
「岩城か。で? 着いたんだな?」
『うん……。改札の前で、待ってるから……』
「分かった。すぐ行く」
「すまんゆーき、今から、十五分ほど出かけてくる」
「えっ? う……うん。でも、こんな時間に、どこ行くの?」
「ナイショ、だ」
「ふあっ……?!」
不安そうな顔をするゆーきの耳に囁いて、不意打ち的に、息を吹きかける。
「心配すんなって、な」
「わ……分かってるけど……」
「すぐ戻る……」
「あ……」
軽く額にキスをして、俺は、待ち合わせ場所の駅に向かった。